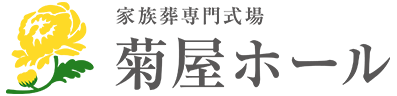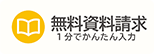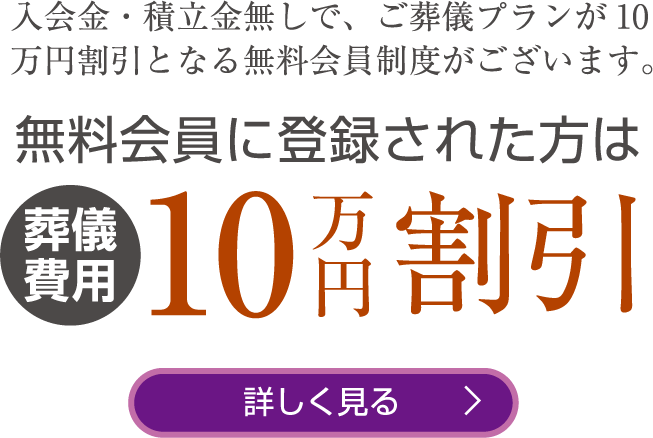葬儀・家族葬ブログ
BLOG
ご葬儀のこと
2025/03/25
喪主と施主の違いは?決め方や役割を解説します。

葬儀を行う際には、遺族の代表として葬儀を取り仕切る喪主を決めます。取り仕切るといっても、「喪主は具体的に何をするのだろう」「遺族の中で誰が喪主になるのだろう」など、わからないことも多いのではないでしょうか。
喪主の役割について理解を深めておくと、いざというときにもスムーズに対応できます。
喪主とは
遺族の代表として葬儀全般を取り仕切る責任者のことで、葬儀にかかわる準備から実施まで中心となって進めていく立場になります。また、通夜や葬儀・告別式だけでなく、その後に続く納骨や年忌法要なども、喪主が中心となって執り行います。
また、喪主は葬儀の主催者として、葬儀社との打ち合わせや遺族の意見のとりまとめなども担うため、葬儀社との打ち合わせまでに喪主を決めておきましょう。
施主とは
喪主と似た言葉に「施主(せしゅ)」があります。施主は葬儀にかかる費用を負担する人のことを指し、ただ支払いをするだけでなく、費用にかかわる葬儀社とのやりとりなど喪主をサポートします。喪主も施主も遺族の代表という点では同じですが、役割が異なるため注意しましょう。
一般的な葬儀の場合、喪主が施主を兼任するケースが多いですが、喪主が高齢である場合に子供が施主を務めたり、故人の勤務先が施主として葬儀の費用を負担したりするケースもあります。
喪主の役割
葬儀全般の責任者である喪主は、その役割も多岐にわたります。1人ですべてを行おうとすると負担が大きくなってしまうため、ほかの遺族や親族のサポートを受けながら準備を進めていくことが大切です。
葬儀に関する内容を決定する
喪主の重要な役割のひとつが、葬儀に関する内容を決定することです。喪主は葬儀の責任者として、依頼する葬儀社や葬儀の種類、参列者、ご遺体の安置場所、供花や芳名板の並び順など、葬儀に関わるさまざまなことを決める必要があります。また、返礼品や弔電のセレクトなどを行うのも喪主の役割です。施主がいなければ、葬儀にかかる代金も基本的には喪主が代表して支払います。
近年では家族葬や直葬・火葬式など葬儀の種類が多様化しており、場合によっては考えの違いから、親族の中でも意見がまとまらないこともあるかもしれません。そのようなときも、遺族代表として最終的な判断を下すのは喪主になります。喪主はどのような形式で葬儀を行うかを決める重要な役割を担うため、決断力や調整力が求められる立場だといえるでしょう。ただし、喪主が高齢である場合などは、葬儀の準備については家族がサポートすることもあります。
親族や関係者に訃報連絡をする
親族や故人の関係者に訃報を伝えるのも、喪主の役割のひとつです。一般的に、家族や故人と近しい方に対しては、危篤段階やご臨終直後に一報を入れます。そのほかの方々には、通夜や葬儀・告別式の日程が決まってから連絡するとよいでしょう。通夜や葬儀・告別式に参列してほしい方、訃報連絡のみとする方など、事前にリストを作成しておくと連絡漏れを防ぐことができて安心です。
なお、家族葬の場合は、葬儀に参列する方以外には、葬儀が終わってから家族葬を執り行った旨を報告することが一般的です。
お寺とのやりとりを行う
仏式で葬儀を行う場合は、お寺とのやりとりが必要になります。お寺や僧侶との日程調整や、戒名の依頼、お布施の受け渡しなどを行うのも、喪主の役割です。菩提寺がある場合は、故人のご臨終後に喪主から連絡を入れ、僧侶のスケジュールを確認しましょう。菩提寺がない場合は、葬儀社に相談するとお寺や僧侶を紹介してもらえます。
参列者へ挨拶をする
一般的に、通夜や葬儀・告別式の終了時のほか、通夜振る舞いや精進落としの際に、参列者に対して喪主から挨拶します。喪主の挨拶では、参列していただいたお礼や故人が生前に受けた厚意に対してのお礼などを伝えます。
なお、家族葬の場合は、参列するのが家族など身近な方々なので、改まった挨拶を省略するケースも少なくありません。
葬儀後の挨拶まわりや年忌法要を行う
喪主の役割は、葬儀の終了後も続きます。まずは、香典をいただいた方への香典返しです。香典返しは当日その場でお渡しする「即日返し(当日返し)」と、後日お渡しする「後返し」がありますが、いずれの場合も喪主が返礼品を手配する必要があります。
また、葬儀後にお世話になった方々にお礼の挨拶まわりを行うのも喪主の役割です。一般的には、四十九日法要や一周忌法要といった葬儀後の法要も、葬儀同様に喪主が責任者となって調整します。
喪主の決め方
喪主を決めるにあたって明確なルールはありませんが、一般的には故人の配偶者が喪主となります。また、配偶者がいない場合や高齢である場合には、その子供やそれ以外の方が務めることもあります。あとからもめないよう、喪主を決める際には家族や親族で話し合って決めましょう。
なお、喪主を決める際の一般的な優先順位は、以下のとおりです。ただし、故人が遺言を残していた場合は、一般的な優先順位にかかわらずその遺志に従います。
喪主を決める一般的な順序
1. 故人の配偶者
2. 故人の子供(長男→次男以降の直系の男子→長女→次女以降の直系の女子)
3. 故人の親(故人が若年者の場合)
4. 故人の兄弟姉妹
喪主が見つからない場合は?
場合によっては、故人に配偶者や子供、兄弟姉妹がいないなど、喪主を務める方が見つからないことがあるかもしれません。そのようなときは、まずは故人と血縁関係の近い順に、喪主を引き受けてくれる方を探します。例えば、故人のおじやおば、孫、甥、姪などが喪主を務めても問題ありません。
親族の中から適任者を見つけることが困難な場合は、代行サービスなどで対応してくれることもあるため、相談してみるとよいでしょう。
まとめ
喪主は遺族の代表者として葬儀を執り行う責任者のことで、役割は多岐にわたります。身内が亡くなった後、葬儀社との打ち合わせを行うのも、喪主の大切な役割です。葬儀にあたっては決めなければいけないことが多く、喪主の負担が大きくなりがちです。葬儀に関する疑問点や不安がある場合は、できるだけ事前に葬儀社へ相談しておくとよいでしょう。
-
葬儀のご依頼・ご相談でお急ぎの方
コールセンター
通話・無料相談
24時間365日対応