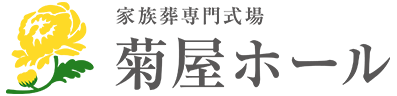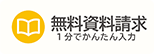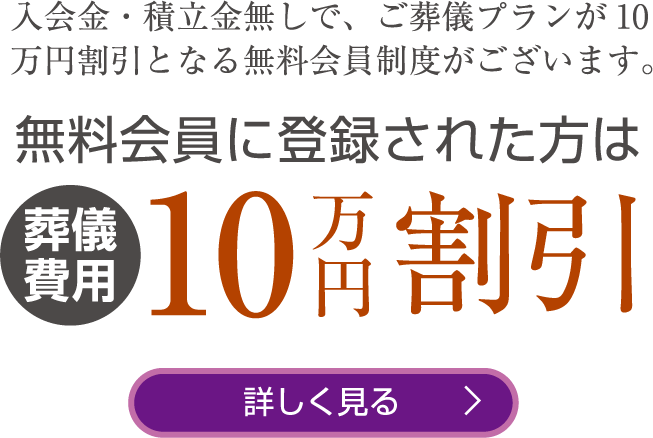葬儀・家族葬ブログ
BLOG
ご葬儀のこと
2025/04/10
忌引き休暇とは?

身内が亡くなったときに取得できる「忌引き休暇」という休暇制度を多くの会社で導入しています。
では、家族や親族が亡くなった際、一般的には何日くらい忌引き休暇を取得できるのでしょうか。忌引き休暇を取得した場合、給与は発生するのかなども気になるポイントかもしれません。
ここでは、忌引き休暇制度で取得できる日数の目安や申請時の注意点のほか、有給扱いになるかどうかを解説します。
忌引き休暇とは
家族や親族といった身内が亡くなった際に取得できる休暇のことです。忌引き休暇に法的な定めはありませんが、身内が亡くなると、葬儀の準備や参列、各種手続きなどのために、どうしても仕事を休まなければならない場面が出てきます。
また、近しい身内を亡くした場合、悲しみやショックも大きいものです。そのため、多くの会社では福利厚生の一環として、就業規則などで忌引き休暇を定めています。会社によっては「服喪休暇」と呼んだり、慶事と弔事の休暇を合わせて「慶弔休暇」としたりするケースもあります。
そもそも忌引きとは、近親者が亡くなった場合に喪に服すことです。昔は身内が亡くなると自宅にこもって身を慎み、故人を悼む風習がありました。忌引き休暇制度は、そのような風習の名残といえるでしょう。
なお、児童や学生にも忌引き休暇はあります。一般的に、忌引きによって学校を休んだ場合は、欠席日数には数えません。
忌引き休暇は有給休暇になるのか?
忌引き休暇を取得した際に給与が発生するかどうかは、会社の規定によって異なります。有給で忌引き休暇を取得できる場合もあれば、そもそも忌引き休暇制度がなく、身内の不幸で休むと欠勤扱いになる会社もあります。
また、忌引き休暇が有給となる会社であっても、就業規則に規定された日数を超えて休んだ場合は無給です。中には、特別休暇として出勤扱いになり、人事評価には影響しないものの、休んだ分の給与は支払われないケースもあります。
忌引き休暇が有給かどうかは、正社員や契約社員、パート、アルバイトといった雇用形態によって規定が異なる場合もあるので、就業規則をよく確認しておきましょう。
なお、会社などに勤めていて一定の要件を満たした方には、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの雇用形態を問わず、法律で定められた所定日数の年次有給休暇が付与されます。勤務先に忌引き休暇制度が設けられていなかったり、忌引き休暇が無給だったりする場合は、年次有給休暇を利用すれば有給で休むことができます。
忌引き休暇の日数の目安
忌引き休暇に法的な定めはなく、休暇制度の対象となる親族の範囲や取得できる休暇日数などは、会社ごとに異なります。多くの場合、「忌引き休暇の対象となるのは3親等まで」などと適用範囲が定められており、亡くなった人との関係性によって取得できる日数が決まります。
忌引き休暇の取得条件や取得日数は、就業規則などに定められているので確認してみましょう。
一般的な例として、忌引き休暇の対象と休暇がとれる日数の目安を紹介します。
配偶者が亡くなった場合
10日
配偶者が亡くなった場合、忌引き休暇で取得できる日数は10日が目安となります。配偶者は身内の中でも特に関わりが深く、亡くなった際の精神的なダメージが大きいことや、葬儀で喪主を務める可能性が高いことなどから、忌引き休暇の日数も長めに設定されているケースが一般的です。
父母や子供など1親等の方が亡くなった場合
5~7日
父母や子供など1親等の親族が亡くなった場合、忌引き休暇で取得できる日数は5~7日が目安です。亡くなったのが実の両親なら7日、子供なら5日など、故人との関係性によって日数の決まりを変えている会社もあります。また、同じ1親等でも、故人が配偶者の父母である場合は取得できる日数が3日など、実の親や子供に比べて取得できる日数が短めになることが一般的です。
祖父母や兄弟姉妹など2親等の方が亡くなった場合
3日
祖父母や兄弟姉妹、孫など、2親等の親族が亡くなった場合に取得できる忌引き休暇は、3日が目安となります。なお、配偶者の祖父母や兄弟姉妹の場合は忌引き休暇が短くなるケースが多く、1日程度であることが一般的です。
おじおばや甥姪など3親等の方が亡くなった場合
0~1日
おじやおば、甥、姪、曾祖父母など、3親等の親族が亡くなった場合、忌引き休暇はないか、取得できても1日程度であることが多いでしょう。ただし、同居していたなど特別な事情があれば、忌引き休暇が認められるケースもあります。
公務員の忌引き休暇の日数は会社員と異なる規定がある
公務員の忌引き休暇の日数は、国家公務員、地方公務員それぞれに規定されています。国家公務員の場合は「人事院規則」に定めがあり、故人との関係性によって取得できる日数が決まり、地方公務員の場合は、自治体によって取得できる忌引き休暇の日数に違いはあるものの、国家公務員の規定に準じるケースも多く見られます。
忌引き休暇を取得する際の注意点
身内に不幸があり、忌引き休暇を取得する際には、以下の点に注意が必要です。休暇が有給扱いになるかどうかが変わることもあるのでしっかり見ていきましょう。
忌引き休暇の数え方を確認しておく
忌引き休暇の日数の数え方は、会社によってルールが異なりますが、亡くなった当日または翌日を1日目として数えるケースが一般的です。また、土日や祝日なども含めて数える会社もあれば、本来の出勤日だけをカウントする場合もあります。ほかにも、連続した日数ではなく、「亡くなった日に1日、翌週の葬儀前後に2日間で、トータル3日間の忌引き休暇が取得できる」ということもあります。忌引き休暇を正しく申請するためにも、日数の数え方を就業規則で確認しておきましょう。
忌引き休暇の申請を忘れないようにする
忌引き休暇の申請は、まず上司へ電話やメールで報告し、休暇取得後に必要書類を提出という流れが一般的です。忌引き休暇の申請をせずに会社を休み、後から「実は身内に不幸があったので」と報告をしても、認められない場合もあるので注意してください。
また、忌引き休暇の取得申請にあたって、提出書類の有無や申請方法は、会社の規定によって異なります。必要書類の例としては、会葬礼状や火葬許可証、死亡診断書などが挙げられます。提出する書類は故人との関係性や自身の立場(喪主か参列者か)などによっても変わってくるので、事前に確認のうえ漏れのないように用意しておきましょう。場合によっては、必要書類の提出がないと有給扱いにならないこともあります。
上司や同僚が通夜や葬儀に参列する場合がある
会社によっては、就業規則や慶弔に関する内規で、従業員の身内が亡くなった場合の葬儀への参列について規定されていることがあります。そのような場合は、忌引き休暇を申請すると、追って会社から連絡があり、上司や同僚が通夜や葬儀に参列する可能性もあります。家族葬などで職場の方の参列を辞退したい場合は、忌引き休暇を申請するときに、その旨も伝えておきましょう。
会社から弔電や香典が送られることがある
上司や同僚の参列がなくても、会社から弔電や香典が送られることがあります。その場合も、忌引き休暇の申請の後に会社から連絡が来る可能性があるので、葬儀の日程や場所などを伝えましょう。
なお、香典を受け取った場合は、お礼に加えて、香典返しを用意する必要があります。また、弔電や香典は辞退することも可能です。
仕事を代行してくれた同僚などにお礼をする
忌引き休暇が明けたら、自分の仕事を引き継いでくれた同僚などへのお礼を忘れずに伝えましょう。同時に、仕事の進捗状況を確認し、必要に応じて取引先などへも連絡を入れます。
身内の不幸はつらいものですが、忌引き休暇を取得していた間は、周りの同僚に負担がかかっていることもあります。お礼の気持ちを伝えるとともに、忌引き明けの出勤時に菓子折りなどを準備すると、より丁寧です。
忌引き休暇は土日も含みますか?
忌引き休暇の日数に土日や祝日を含むかどうかは、会社によって規定が異なります。会社によっては土日や祝日なども忌引き休暇に含める場合もあれば、本来の出勤日だけをカウントする場合もあります。忌引き休暇の数え方は就業規則などに定められているため、事前に確認しておくことが大切です。
-
葬儀のご依頼・ご相談でお急ぎの方
コールセンター
通話・無料相談
24時間365日対応