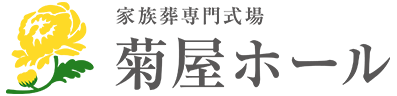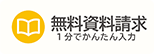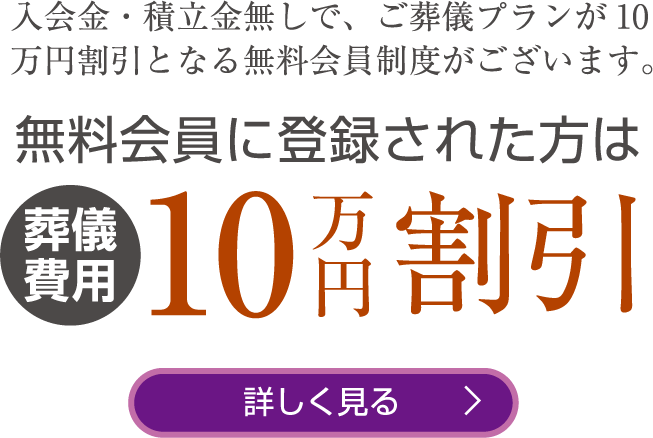葬儀・家族葬ブログ
BLOG
マナー
2025/10/25
遺骨の粉骨とは?

故人のご遺骨を散骨したいと考えている場合などに、必要になるのがご遺骨を砕いて粉末状にする「粉骨」という工程です。粉骨は自分で行う方法もありますが、業者に委託することが一般的です。
自分で行う場合と、業者に委託する場合の両方をご紹介します。粉骨後の供養方法もお伝えします。
粉骨をする前に知っておきたい注意点
家族や親族にも理解を得ておく
故人のご遺骨を砕くという行為に抵抗を感じる方もいるため、粉骨をする場合は、家族や親族にも説明し、事前に理解を得ておくことが大切です。勝手に行ってしまうと後々、親族間のトラブルに発展してしまう可能性があるため注意しましょう。
粉骨は、できれば業者に依頼する
粉骨には有毒物質の除去など専門的な技術が必要なことがあります。ただ砕くだけなら自分でできないこともありませんが、なるべく業者に委託した方が安心です。
迷いがある場合は一旦やめて、よく考える
一度粉骨をしてしまったご遺骨は、元に戻すことはできません。もし、粉骨に不安や迷いがあるのであれば、一旦立ち止まって、よく考えてみることも大切です。
粉骨とは?
ご遺骨を粉末状に細かくすることを、粉骨といいます。通常、お墓に納骨する際には、ご遺骨を骨壷に収めた状態で墓下にあるスペースに納めますが、遺骨を海や山に撒く散骨を考えている場合など、供養方法によっては粉骨が必要になります。
粉骨のメリットとデメリット
メリット
- 容積が減ることで納骨場所の省スペースにつながる
- 散骨や手元供養など、供養の選択肢が増える
- 家族や親族で分骨する場合、遺骨の状態よりも平等に分けやすい
デメリット
- 粉骨することに抵抗がある場合、精神的苦痛を伴う
- 一度粉骨してしまえば元に戻すことはできなくなる
- 業者に委託する場合は費用が伴う
- 自分で行う場合は時間と労力がかかる
粉骨を委託する場合の費用と注意点
粉骨を業者に委託する場合、気になるのが費用相場と業者の選び方だと思います。ここでは粉骨の費用相場と、業者選びのポイントをお伝えします。
費用相場
粉骨を業者に依頼する場合の費用は、1〜3万円程度が相場となります。3寸ほどの小さな骨壷であれば1万円程度、6〜7寸の大きめの骨壷であれば2〜3万円程度など、ご遺骨の量によっても費用は異なります。また、「乾燥が必要か」「立ち合いの希望があるか」「手作業か機械作業か」「お戻しは郵送か」など、各種条件によって費用が変わってきますので、まずは見積もりを依頼してみましょう。
粉骨業者の選び方
粉骨業者を選ぶときは、まず粉骨を専門に行っている業者かどうかを確認しましょう。その上で、事業所名や料金が明確かを確認することも大切です。後述しますが、粉骨はただ骨を砕くだけでなく異物除去や有害物質の処理なども必要な場合があります。それらも含めて料金が明示されている業者の方が安心です。
また、ご遺骨を業者に引き渡す方法は、郵送と持ち込みの2択となりますが、ご遺骨を郵送することに抵抗がある場合は、持ち込みのできる範囲内の業者に絞って探すという方法も有効です。
粉骨業者の中には、立ち合い粉骨ができる業者もありますので、自分の目で見届けたいという方は、そのような業者を選ぶこともおすすめです。ただし立ち合いは、業者によっては有料の場合もあるため、事前に料金を確認しておきましょう。
委託する場合の流れ
業者を選ぶ
↓
郵送または持ち込みでご遺骨を引き渡し
↓
業者にて遺骨の状態を確認後、粉骨作業が行われる
↓
包装して完了
↓
郵送または手渡しでお戻し
お引き渡しからお戻しまでは、手渡しの場合は最短で約1時間程度、郵送の場合は1週間程度かかるイメージです。
粉骨を自分で行う場合の流れ
ご遺骨を袋に入れてカナヅチやハンマーなどで砕く
↓
袋から出してすり鉢などでさらに細かくしていく
↓
目の細かいふるいにかけて異物を取り除く
目安としては、2mm以下程度
最近は、粉骨用の機械をレンタルしたり「散骨キット」を購入したりすることもできますが、初めての人には難しいことも多く、異物が混入していると機械を壊してしまうトラブルなども考えられるため注意が必要です。
粉骨後の供養方法
一般的な墓石のあるお墓に納骨する場合は、お墓の下のカロートという場所に骨壷ごと納めるため粉骨する必要はありませんが、供養方法によっては粉骨が必要な場合があります。ここでは、どのような場合に、粉骨が必要になるのかについてお伝えします。
散骨をする場合
ご遺骨を海や山などの自然に撒く「散骨(さんこつ)」では、遺骨をパウダー状の粉骨にすることが義務付けられています。もし粉骨せずに遺骨のまま撒いてしまうと、刑法190条に定められている「遺骨遺棄罪」に問われてしまう可能性があるので注意しましょう。
ちなみに、散骨は、粉骨さえすればどこでも好きなところに撒いてよいというわけではありません。海でも山でも条例や法律に触れない場所で、マナーを守って行わなければ、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。そのため、専門業者が提供するサービスを利用するようにしましょう。
樹木葬の場合
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木を墓標とするお墓の一種です。特定の樹木の下にご遺骨を埋葬するもので、家族や個人単位で、個別に一本の樹木を墓標としている場合と、複数のご遺骨が一本の樹木を墓標としている場合とがあり、その中でも骨壷のまま埋葬するタイプと骨壷から出して埋葬するタイプがあります。
散骨と同じ自然葬の一種ですが、樹木葬は墓地埋葬法に則ってお墓として認められているため、散骨とは違って粉骨しないと法律違反になってしまうということはありません。ただし、墓苑によっては、スペースの関係で粉骨しなければならないこともあるようです。また、より早く自然に還りやすくする目的で粉骨をするケースもあります。粉骨が必要かどうかは、契約時によく確認しておくとよいでしょう。
納骨堂に納骨する場合
納骨堂とはお墓の一種で、個人や家族単位で遺骨を収蔵しておく施設のことをいいます。ロッカー式や棚式、仏壇式などさまざまな納骨スタイルがありますが、いずれも屋内の施設であることが特徴です。納骨堂では、基本的には骨壷のまま納骨しますが、骨壷の数が多くなってしまった場合に、粉骨することで容積を減らして、一つの骨壷にまとめて納骨する場合があります。そのような場合に、納骨堂でも粉骨が必要になることがあることを覚えておきましょう。
手元供養する場合
より身近な形で供養する方法として、最近は、遺骨ペンダントなどのように普段から身につけられるアクセサリーや、ミニ骨壷などに収めて自宅でご遺骨を保管する手元供養も人気があります。手元供養の場合、粉骨が必須というわけではありませんが、アクセサリータイプの場合は、粉骨をしていないとご遺骨を収められない場合が多くなっています。
また、粉骨をすることで有害物質を気にせず手元に置いておけるといったメリットもあるため、メリット・デメリットを考えて選択をするとよいでしょう。
分骨する場合
ご遺骨を複数の骨壷に分けて保管することを分骨といいます。たとえば兄弟がいて、それぞれが身近な場所に遺骨を保管しておきたいと望んだ場合や、菩提寺が遠方にあり、遺骨の一部を手元供養として身近な場所に保管しておきたいと望んだ場合などに、分骨が行われることがあります。その場合、遺骨のままの状態では均等に分骨することができないため、分けやすくするために粉骨をするケースが多くなっています。
-
葬儀のご依頼・ご相談でお急ぎの方
コールセンター
通話・無料相談
24時間365日対応